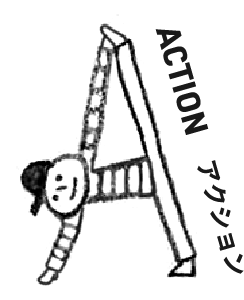実施内容
私たちが堀田農園さんで体験させていただいたのは、原木の水漬け、棚上げ、収穫、原木の片付け、選別、加工の作業でした。
~原木の水漬け~
しいたけ栽培の最初の過程は、原木の水漬け作業です。
しいたけ菌を入れて出番を待っている状態の原木を1日水に漬けます。水漬けをして原木に刺激を与えることで、しいたけがたくさん生えてくるようになります。水槽に入れるためには、原木を鉄枠に詰める作業をしなければいけないのですが、これが本当に難しい!原木にはさまざまな太さや形があり、真っ直ぐなものばかりではありません。曲がっている原木が鉄枠からはみ出ないようにしたり、原木と原木の間に隙間ができないように詰めたりと、よく考えながら作業をする必要がありました。

~棚上げ~
水漬けした原木をハウス内の棚に1本ずつ並べていきます。原木は1本あたり5キロ以上の重さがあると言われています。水を吸って少し重くなった原木を持ち上げるのは体力の必要な作業です。このとき、原木を太い→細い→太い…と交互に並べていくことがポイントです。太い原木が偏って並んでいると、しいたけが生えてきたときに近くの原木に当たってしまい、見た目が悪くなってしまいます。実際に収穫していたときに、生えてきたしいたけが上の棚にある原木に触れてしまい、形が悪くなっているしいたけがありました。見た目が悪くなるとそのままでは販売できなくなるため、慎重に棚上げすることが大切です。

~収穫~
大きさを問わず、しいたけのかさが開いていて内側の白いひだが見えているものを選んで収穫します。私たちが実習に参加した9月中旬の時点では、毎朝、買い物かご6個分くらい、約30キロの量を収穫することができました。昨年参加した8月末〜9月上旬はまだ暑い時期だったこともあり、収穫できるしいたけが少なかったことを覚えています。自然を相手にする仕事であるため、気候に左右されて収穫量が変わってしまうことが難しさであることだと思いました。
~原木の片付け~
収穫を10回程くり返した後の原木は、そこで役目を終えるわけではありません。最後は、冬場に常に稼働させなければならない薪ストーブの燃料として活躍します。もう一度、鉄枠を用いて棚から移動させ、ハウス内の壁側にきれいに積み上げていきます。堀田農園の原木はおよそ1万本もあるため、隙間なく、高く積み上げなければハウス内に納めることができません。体力と頭を使いながらの作業となります。原木を運ぶ際に電動のカートを使用するのですが、カートの動かし方も難しかったことの一つです。原木を積むと、カートの高さは私の目線より少し低いくらい、だいたい140cmの高さになります。ハウス内の通路は狭く、カートがギリギリ通れるくらいの幅であるため、少しでも動かす方向を間違えると棚や壁に当たってしまいます。私も何度もぶつけてしまい、習得することも難しさを感じました。

~選別~
収穫したしいたけの中から、商品として販売できるきれいな見た目のしいたけを一つずつ目視で確認して選別していきます。小さすぎないかつ、かさが開きすぎていないしいたけが出荷されます。きれいなしいたけの基準は狭く、選別した結果、収穫した量に対して商品にならないしいたけの多さに驚きました。
~加工~
商品としてそのまま出荷することができなかったしいたけは、手作業でスライスして乾燥しいたけとして販売しています。そうすることで、形が整っていない部分を除くことができ、おいしい部分を無駄にすることなくお客さんに届けられます。
堀田農園で栽培しているしいたけは原木栽培のしいたけで、菌床栽培よりも手間暇かけて栽培されていることが特徴です。手間暇かけて栽培されているが故に、原木栽培を辞めてしまう生産者が多く、現在はしいたけ農家の約9割が菌床栽培で、原木しいたけは全体の約1割しか栽培されていません。しかし、菌床栽培ではしいたけの成長も統制されたものとなってしまい、しいたけにとって理想の成長環境とは言えません。原木栽培ならストレスなく、そのままの自然環境を吸収して育つため、しいたけにとってはのびのびと成長することができます。こだわりを持って原木しいたけを栽培されている堀田さんの想いや熱意を感じることができた機会となりました。

参加者の声
昨年もしいたけ栽培のお手伝いをさせていただいたので作業の感覚は体が覚えていたのですが、体力が必要な作業が多く、毎日行うことの大変さを改めて感じました。原木栽培にこだわりを持って取り組まれていたり、原木しいたけの美味しさを伝えるために活動していることを学び、私も堀田さんの作るしいたけの美味しさを広めていきたいと思いました。みなさんもぜひ一度食べてみてください!
(記事を書いた人 あやや)