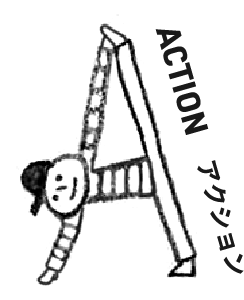実施内容
今回の羊鶏クラブは、1年間みんなでお世話をした羊1頭と鶏3羽の命をいただく、という特別な回でした。そんな1日をご紹介します。
※動物の解体に関わる写真が掲載されています。
【午前】
羊は自分たちで絞めることはできず、事前にと畜場で解体されていました。羊の肉がパーツごとに袋詰めされているものを、子どもたちと一緒に羊の頭から胴体、足の方まで並べて観察しました。

そのあとは2チームに分かれて活動を行いました。1つのチームは鶏小屋の屋根を補強する作業を行いました。前回、鶏を寒さから守るために、小屋にビニールや屋根を取り付けました。その屋根に傾斜をつけて雪が滑りやすくなるようにするために、木材を使ってパーツを作り、屋根の上に設置しました。主に子どもたちが電動ドライバーを使ってパーツを作っていました。使い方を知っている子が、初めて電動ドライバーを持つ子へ手を支えながら教えている姿が印象的でした。

もう一方のチームでは、羊の胃の下処理を行いました。お湯に浸しながら手やスプーンを使って、ヒダの中にある汚れを取り除きます。胃にはヒダがいくつもあり、汚れも力を入れてこすらないと落ちないので、根気がいる作業でした。

【午後】
鶏たちに最後の餌を食べさせ、一羽ずつ絞める時間となりました。鶏の頭を上に反らして、頸動脈をナイフで切り、出血させることで絞めます。失血死した後は、70℃くらいのお湯に浸けて毛穴を開かせ、羽が抜けやすいようにしてから手で羽をむしりました。最後の3羽目は、子どもがスタッフの方とナイフを持ち、絞めることに挑戦していました。


鶏を絞め終わって大人たちがメインで羽をむしるまでの一部始終の間、子どもたちはそれぞれの過ごし方をしていました。作業に飽きている子もいれば、怖がりながらも見守る子、その空間にはいるけど別のことをして過ごす子もいました。子どもたちが多くを声にする訳ではないので推測かもしれませんが、それぞれがそれぞれの想いを持ちながら同じ空間にいるような感じがしました。作業が少し落ち着いた後は、外にあるハンモックでゲームをしたり、鶏の羽を並べたり様々なことをして遊んでいました。

絞めたあとは鶏を捌きました。今回ボランティアとして参加した私たちも経験させてもらいました。一般的に家庭で使われるような包丁を使い、ほんの少し見えるような筋を頼りにパーツ毎に切り分けていきます。慣れない私たちにはすごく神経を使う作業で、約2時間ほどかかりました。鶏の姿から、少しずつスーパーなどで見かけるお肉の姿に変わっていく様子を見て、「命をいただくということ」に少し触れられたような気がしました。

その鶏と羊のお肉を使って、たくさんの子ども、大人で協力してご飯を作りました。鶏肉のサラダ、鶏のだしを使ったスープ、羊の肉のシチュー、焼いた羊の肉といったメニューでした。食べる前には今回いただく羊と鶏の紹介がありました。人間の都合ですが、子どもを産むことができない雄の命を今回はいただくとのことでした。みんなで「いただきます」をして、命に感謝しながら、いただきました。美味しいのは勿論のこと、生死がこんなにも身近だったことに気付かされました。色々な想いを抱きながら噛み締めた特別な時間となりました。


(記事を書いた人 リオ、あらた)
参加者の声
今回初めて活動に参加しました。参加するまでは、鶏を絞めるということにドキドキしていましたが、活動に参加し、さっきまで生き物だった鶏がだんだんと普段見るようなお肉の姿になっていくのを見ることで、”生き物をいただいている”ということを改めて感じました。とても貴重な経験ですし、子どもがこれを経験できていることがすごいなぁと思いました。また、いろんな人と交流することができ、とても刺激的な1日でした。(りほ)
過去の記事はこちら!