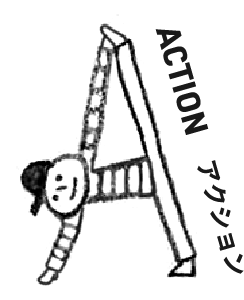滞在中の気付き
うめ:みんなが厚真町に滞在している期間に、厚真・上厚真の放課後児童クラブに行ったことを聞きました。そこで何か気付くことはありましたか?
ちゃんまな:厚真と上厚真の2つの放課後児童クラブに行く機会を設けて頂き、子どもたちとの遊びやお話から自分が知らなかったことを教えてもらったり、放課後児童クラブの支援員の方々や実習のメンバーからは、子どもとどのように関わっているのかを学ぶことができました。
同じ町の放課後児童クラブといっても、それぞれ特徴があり、その中でも印象的だったことが外遊びです。厚真の放課後児童クラブでは子どもたちは併設している森の中で遊び、上厚真では遊具で遊んでいました。厚真には遊具はありませんでしたが、木を使って自分たちで秘密基地を作ったり、ニンジンを育てたり、虫を捕まえたりして遊んでいました。遊具がないからこそ、子どもたちがやりたい遊びを自分で考え、実現してみる環境が整っていて、遊びの創造力が広がるなと感じました。
私自身、子どもたちから虫の話をたくさん聞き、知らなかった虫を知ることができたことで、子どもから教えてもらうことが多くあると学びました。また、支援員の皆さんもすごく協力的で、子どもたちの要望をどうにか実現できないかと一緒に考えたり、アドバイスしたりしている姿が印象的でした。
上厚真では、遊具を見てすごく驚いたことがありました。子どもたちの身長では届かない高さの大きなブランコがあったのですが、階段も梯子もついていませんでした。子どもたちはどのようにブランコに乗るのかなと思ったのですが、自分の力で少しずつ登れるようになると聞きました。簡単には登れない高さのブランコに自分の力で乗れた時の達成感や、自分で危ないと判断する力が身に付けられるのだと感じました。また、上厚真はこども園と併設しているので、小学生が園の幼児と一緒に遊んだり、「危ないよ」と教えてあげるお姉さん、お兄さんの姿も見ることができました。
うめ:私も厚真の放課後児童クラブに行った時には子どもたちが馬に乗っていたり、秘密基地を作って遊んでいたり、のびのびと自由に遊んでいるイメージがありました。昨年も参加していたあいこはどうでしたか?
あいこ:私は昨年から続けて、今年も放課後児童クラブにお邪魔させていただいたので、昨年との変化を感じました。それは支援員の方が入れ替わっていたことや、施設内の掲示物が子どもたちが作った作品や行事の写真でいっぱいになっていたことです。
実際に子どもたちと支援員の先生が掲示をしていて、子どもたちが最近あった行事の写真を見ながら、「このときはね~」と話している姿も見られました。放課後児童クラブの掲示物が子どもたちが作っていたものだったり、関わっていたりするものがあるというのが、子どもたちと一緒につくるという感じがしてすごく印象に残っています。
また、森にも変化がありました。子どもたちが作っている秘密基地や馬の練習場が作成中のままになっていて、様々な活動や遊びが継続するように「そのまま」の形で残されているのが、子どもたちの自由な発想を広げることにつながるのだと思います。「次はこうしてみたい」「あれをつくりたい」という意欲を高めることで、昨年よりも子どもたちに寄り添った放課後の作り方になっているなぁとすごく感じました。

うめ:私も昨年、少し放課後児童クラブにお邪魔しましたが、今年は子どもたちと自然の距離がすごく近くなったなと感じ、このようなことができるのも厚真町ならではなのかなと思いました。放課後児童クラブ以外での子どもたちの様子を知る機会はありましたか?
のん:滞在中に、厚真神社のお祭りに行く機会がありました。子どもたちが日本舞踊を踊っていたり、和太鼓を叩いたりしていました。子どもたちはみんなかっこよくて、うるうると泣きそうになっていました。
滞在場所を提供いただいた堀田さんから、習い事として週に1回、地域の子どもから大人までが集まって練習する場があることを聞きました。私たちは、習い事といったら子どもだけが集まって先生に教えてもらうイメージが強かったのですが、そこでは同世代だけでなく様々な年代の方と教え合ったり、楽しくお話することができて、そこがみんなの居場所になっているんだなと強く感じました。
また、日本舞踊や和太鼓を習い事としてみんなで学んでいることも印象的でした。日本文化を子どもたちが楽しく学べることで、堅いイメージの印象をもつのではなく、続けていきたい文化だと継承していくという大切なことにもつながっているのかなと感じました。
「学び合う」居場所づくり
うめ:なるほどなるほど。今、のんの話で子どもから大人までが集まっているという話があったけど、それは多世代が学び合う生涯学習にも繋がっているなと感じました。他にも地域の中で子どもや大人が交流する場があったそうですね!
あいこ:滞在期間中に地域の方が集まる英会話教室とけん玉クラブに参加したのですが、そこでも地域の大人と子どもたちが交流し合う場になっていました。英会話教室では、厚真町教育委員会の方が中心になって、学校のALTの方を講師として初心者と上級者の2つのクラスを開講していました。対象はどなたでもということで、幼稚園児からご年配の方まで参加していました。
私たちは初心者クラスを見学させていただいたのですが、このクラスは親子で来ている方々が多いことから、会話を交えながらお互いに教え合う雰囲気がありました。また、じゃんけんやだるまさんがころんだといった子どもたちの身近な遊びを英語でやっていて、和気あいあいと楽しく英語を学ぶことができる環境だと感じました。
けん玉クラブは、実習でもお世話になった厚真町教育委員会の斉藤烈さんが中心となり、週に1度開かれているとお聞きしました。「いつでも、どこでも、だれでも」ということで、私たちが見学させていただいた日は、子どもたちが親子で参加していたり、幼稚園の先生、地域おこし協力隊として厚真町で活動されている方、けん玉日本一の方も参加していました。職種も年齢層も様々な方が集まっているけん玉クラブなのだなという印象でした。けん玉クラブは、厚真町を飛び出して他のまちでもイベントを開催しているとお聞きして、どこでも、だれでも、集まれるような居場所がつくられているんだなと感じました。けん玉クラブに参加してみて、けん玉が上手な方もたくさんいらっしゃるので上達することはもちろんだと思いますが、技術の上手い、下手は関係なく、週に1回気軽に集まれるこのような場所があることに一つの大きな価値があると実感しました。
様々な方と出会い、お話させていただく中で、私自身もこれからこんなことやってみたいと思ったり、日頃の悩みを相談してみたり、たくさんの刺激をもらえる場だなと感じました。最初は英会話教室もけん玉クラブも、週に1回開催されている習い事のようなものだと聞いていましたが、行ってみたらもっと深いところに、この教室が開催されている意味や価値があるんだなと感じることができました。

うめ:けん玉クラブや英会話教室を通して、ひとつのより所ができているんだなと感じました。あややはどうでしたか?
あやや:私は、厚真の放課後児童クラブに隣接している、森を使った「森のひろば」に参加しました。森のひろばは地域の教育に携わる方が集まり、子どもたちにさまざまな体験を提供している場所でした。火起こし体験、ブランコ作り、馬との触れ合い、木や松ぼっくりを使ってアクセサリーを作る体験もできます。
森のひろばに参加して、大自然のなかで自然とふれあえる体験が身近にあるというのは貴重なことだなと感じました。また、火起こしなどで木を使うことは、理科の授業などの学びにも繋がっていくことなのかなと感じました。学校の勉強で火が付く原理を学ぶかもしれないけど、実際に自分で体験しながらそれを学べることは、自分ごととしての学びに繋がることだなと思いました。また、森のひろばのなかで鬼ごっこをしている子どももいました。
準備された遊びを楽しむことはもちろん、「今はこの遊びの時間」という縛りがなく、自分の好きなことをやっていいという場所では、自分の興味のあることに全力で取り組むことができるので、そこで得られたことを次の学びに生かしていくことができるんだなと思いました。
うめ:厚真の子たちはすごいわんぱくな印象があって、今までの話を聞くと子どもたちの生活に外で遊ぶ機会が当たり前になっているんだなという印象を受けました。ただ楽しいだけではなく、地域の中での大切なコミュニティになっているというのはすごいことだと思います。厚真町では最近またおもしろい取り組みが行われていると聞きました。
のどか:そうですね。2024年9月に子どもたちの体験型カフェとしてリニューアルした「地域食堂Dinoご飯」に行かせていただきました。「Dino旅館」さんの食堂スペースで開かれているこの地域食堂は、元々旅館に宿泊しているお客さんと厚真町の方々が交流する場や、様々なイベントの開催場所として活用されていたそうなんですが、ちょうど私たちが伺った日は、子どもの「体験型カフェ」としてリニューアルオープンされた日でした。
「子ども主体」というのが趣旨なので、来ていた小学生がこの日のメニューだったかぼちゃ団子づくりから接客、配膳までの一連の流れを行っていて、私たちはお団子づくりと接客のマニュアル作成のお手伝いをしてきました。初めは、小学生が接客の文言を考えるのは正直ハードルが高いのではないかと思っていました。ですが、実際は接客する姿を思い浮かべながらセリフを考えるのを楽しんでいる姿や、接客が上手くできたときの誇らしげな顔を見て、私たちが思っている以上に子どもたちは成長していて、その力を発揮する機会を作ることが大人やまちの役割なんだなと気づきました。
特にこの日、住民の方からお聞きした6年前の震災のお話が、強く印象に残りました。函館でメディアを介して状況を把握するのと、現地で被災した方から直接被害の状況を聞くのとでは、同じ情報でも全く言葉の重みが違うように感じました。厚真町ではこれから震災を知らない子どもたちが増えていく中で、次の世代に被災した方の教訓を継承していくことが課題であるように思いました。その点で、地域食堂は「子どもの自主性を身に付ける場」や「地域の方々の居場所」としてだけでなく、「多世代交流を通じて、震災の教訓をはじめとするまちの歴史や文化を知る機会を創出する場」としても大きな意味をもつ取り組みになるのではないかと思いました。
うめ:Dino旅館さんは私も昨年お邪魔させていただいたことを覚えています。今の話を聞き、また新たな取り組みが始まっているんだなと知って、この場所がさらに広がっていけばいいなと思っています。

参加者の声
今回、厚真長期滞在プログラムに参加し、ほぼ毎日厚真町の子どもたちや地域の方と交流し、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。子どもたちと一緒に遊んだり、地域の皆さんとお話して「私もこんなことやってみたい!」と日々たくさんの刺激、学びをもらいました。卒業後は教員として進んでいきますが、厚真長期滞在プログラムでの学びを糧に前に進んでいきたいと思います。(のん)
昨年に引き続き2回目の参加でした。昨年、放課後児童クラブで一緒に遊んだ子どもたちが私のことを覚えていてくれたことがとても嬉しかったです。子どもたちの1年での成長を感じたり、上厚真小の放課後児童クラブの特徴、それ以外の子どもの活動機会など、厚真町の教育について多くのことを知ることができました。今回学んだ「子どもの居場所」や「成長機会」などを、大学で学んでいる福祉にも生かしていきたいと思います。(あやや)
長期滞在プログラムに参加し、厚真町でたくさんの人生初体験をしました!火起こしをしたこと、馬に乗ったこと、流れ星を見たことなど、地元ではできないことを体験させていただき、とても刺激がある2週間でした。虫の知識や放課後児童クラブにあるゲーム、流行りを教えてもらうなど、子どもたちから学ぶことがたくさんありました。今までは教育に大切なのは環境だと思っていましたが、子どもたちが遊びを作り出している姿を見て、学びは日々の遊びの中にあると感じました。この実習の経験を大学で学んでいる地域学やまちづくり論に生かしていきたいと思います。(ちゃんまな)
長期滞在プログラムに参加し、1番印象に残っているのは子どもたちが自然の中でのびのびと「自分がやりたいこと」をして遊んでいた姿です。子どもたちの無邪気な姿から元気を貰い、時には一生懸命に何かに挑戦する姿に感動させられることもありました!厚真町の教育の在り方から、子どもたちの「自主性」を尊重し、もっている力を発揮するお手伝いをするのが大人の役目なのだと学びました。実習を経て得た学びや経験を、大学やゼミナールでの活動に生かしていきたいと思います。(のどか)
昨年から厚真町に関わらせていただき、子どもたちと遊ぶ中で厚真町の教育について学ぶことができた貴重な時間でした。お祭りに行ったときや英会話教室、けん玉クラブに参加させていただいたときは、放課後児童クラブの子どもたちが声をかけてくれたり、地域の方々が大学生の取り組みに興味を持ってくださったりと、厚真町の皆さんの温かさに触れました。また、意欲的な方々とお話しさせていただくことで、自分には何ができるかと日々模索した実習になりました。春から小学校の先生になるので、私も誰かの人生や生き方に前向きな影響を与えられるように頑張っていきたいと思います。(あいこ)
厚真町に関する過去の投稿はコチラ!